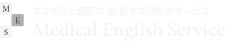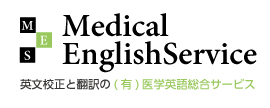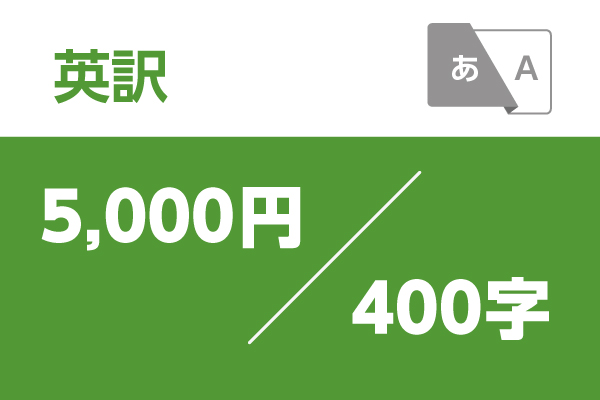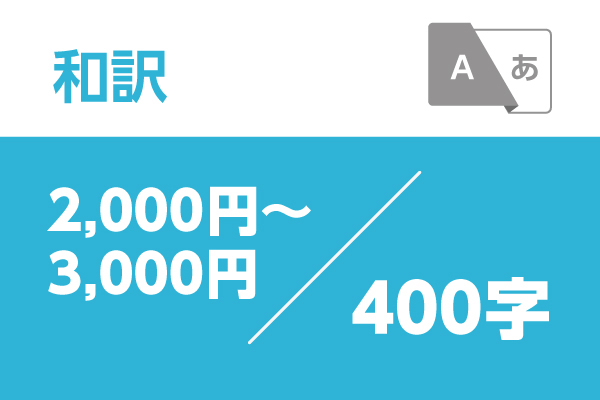研究者にインパクトを与えた論文数 日本の低迷と中国の躍進~科学技術指標2021 ~
科学技術指標2021とは
2021年8月10日、文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、「科学技術指標2021」を取りまとめ公表しました。これは、主要7か国(日本、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、中国、韓国)の科学技術活動について、客観的・定量的データに基づいて体系的に分析した基礎資料となるもので、毎年作成、公表されています。
ここでは、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育と科学技術人材」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の5つのカテゴリーに分類し、約160の指標の状況を表しています。なお今回の「科学技術指標2021」では、「主要国における総付加価値に対する各産業のシェア」、「主要国への商標出願状況と主要国からの商標出願状況」等が新たな分析指標として公表されています。
主要指標の動向は
約160の指標のうち注目すべき指標として挙げられるのが、「研究開発費」、分数カウント法による「研究者数」、「論文数」、2か国以上への特許出願を表す「パテントファミリー数」、「注目度の高い論文数(Top10%補正論文数)」等です。これらの指標において、主要国中の日本の順位としては、「パテントファミリー数」については1位、「研究開発費」、「研究者数」、「論文数」については、アメリカ、中国などに次ぐ3位、またはドイツやイギリスが加わった各国に次ぐ4位で、これらは科学技術指標2020と同様の順位を維持した形です。しかしながら、「注目度の高い論文数(Top10%補正論文数)」については、昨年からひとつ順位を落とし、世界10位という結果となりました。またこの指標では中国が初めてアメリカを上回って世界一位となりました。なお1位からの順位は、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、カナダ、フランス、インド、日本となっています。
ただし、順位だけで見ると前回との違いはありませんが、実態としてその伸びに着目すると、日本は主要国に比べて小さいことも明らかになっています。
研究開発費にみる状況
研究開発費は、企業、大学、公的機関といった部門別にまとめられていますが、日本では特に大学部門、公的機関での伸びが小さくなっていました。
企業部門では国により拡大している産業が異なっています。例えば日本やドイツは「輸送用機器製造業」、アメリカは「情報通信業」、フランスやイギリスでは「専門・科学・技術サービス業」、中国や韓国では「コンピュータ、電子・光学製品製造業」となりました。また、日本、ドイツ、中国、韓国では製造業に、フランス、イギリスでは非製造業に、アメリカは製造業に重みがありつつ非製造業にも一定の規模があることが明らかとなっています。
研究開発人材にみる状況
研究開発人材も、企業、大学、公的機関といった部門別にまとめられていますが、日本では大学部門や公的機関部門の研究者数の伸びが小さく、いずれの部門においても中国の規模や伸びが著しく大きくなっています。
企業部門における日本の現状としては、研究者に占める博士号保持者の割合がほとんどの産業で5%を超えるアメリカに比べて低い水準となっており、日本ではほとんどの産業で5%未満となるようです。なお、博士号取得者数も2006年をピークに減少傾向にあり、博士課程入学者も減少しています。
また、女性研究者数について、その割合は主要国に比べ低くなっていますが、新規採用研究者に占める女性研究者の割合は増加傾向にあります。
研究開発のアウトプットにみる状況
国ごとの貢献度を見る論文数では、前述のとおり日本はその数が横ばいで、他国・地域の増加の影響もあり、順位を下げた結果となりました。Top10%補正論文シェアの高い分野を見てみると
●日本:物理学、臨床医学、科学
●アメリカ:臨床医学、基礎生命科学、物理学
●中国:材料科学、科学、光学、計算機・数学
となっています。
1位を維持したパテントファミリー数では、中国のシェア増加によって、10年前に比べ日本の「情報通信技術」、「電気工学」のシェアが低下していることがわかりました。中国は順位こそ第5位ですが、その数は着実に増加しています。なお、日本も含め各国のパテントファミリーが最も引用しているのはアメリカの論文であるということもわかっています。さらに中国のパテントファミリーでは、自国の論文を引用している割合は主要国に比べて低い傾向にあり、パテントファミリーから引用されるシェアも論文数のシェアに比べると小さいことも分かっています。
今回の統計では、辛うじて順位を維持し続けるも伸びが感じられず低迷を続ける日本と、明らかな伸びと躍進を見る中国との違いが明確となりました。日本にも1位を維持した指標がありましたが、特に科学水準のひとつの判断目安ともなり得る「Top10%補正論文数」の順位を落としてしまったことは、世界の中で強い影響力や存在感を印象付けることはできず、大きな課題を残す結果となったといえるのではないでしょうか。