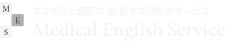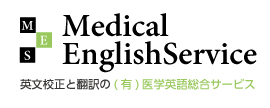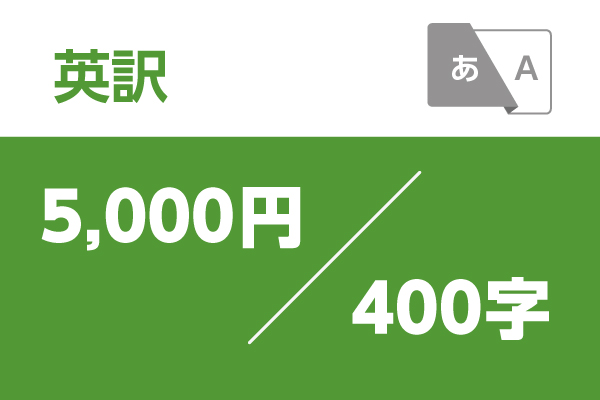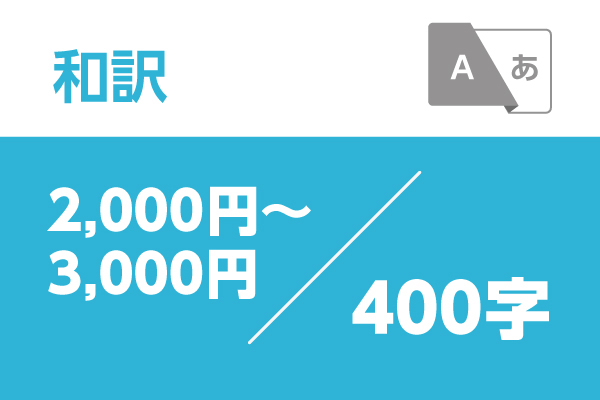統計的に有意差が認められないときは
研究を進めた結果、明らかに有意差が認められた場合は、新規性があり、その分野において役立つ研究であると自信をもって発表できます。その一方で、統計的に有意差が認められない結果が出たときは、どのようにして論文にまとめればよいのか悩むことでしょう。
しかし、有意差が認められなかった研究も決して無駄ではなく、科学の発展のために重要な意味を持っているのです。大切なのは、考察のセクションをどのようにまとめるかです。統計的に有意差が認められない結果が出た場合の対処法をご紹介します。
統計的な有意差とは
「統計的な有意差」とは、単なる偶然によって得られた値ではなく、得られたデータが統計的にも意味のある差を示していることをいいます。医学論文においては、「有意差がある/ない」または「95%信頼区間」といった用語で表現されます。
統計的な有意差を判断するために、統計学の仮説検定という手法で用いられる「p値」という値が用いられます。これは、繰り返し実験を行って得られた結果の整合性を示しており、それぞれ次のように考えられています。
・p値が0.05未満の場合=有意差がある
・p値が0.05以上の場合=有意差がない
「統計的に有意差がない」というのは、研究や実験において得られた結果が、偶然や誤差の範囲内で説明できる可能性が高いということを意味します。具体的には、「p値(p-value)」が0.05よりも大きい場合、その結果は偶然の産物である可能性が高く、統計的に有意ではないと判断されます。
例えば、ある薬の効果を調べる実験で、p値が0.07になったとします。これは、実験で得られたデータが偶然起こる確率が7%であり、5%より高いため、「薬に効果がある」と結論づけることができません。
ただし、p値が0.05を超えて有意差が認められない結果が出た場合でも、論文としてまとめて世に出すことには意味があります。実際、近年では有意差が認められなかった研究であっても、科学の発展のためにアクセプトするジャーナルも増えているといいます。
2016年には、米国統計学会(ASA)がp値の誤用に警鐘を鳴らすため、“The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose”という声明を出しました。「p<0.05」つまり有意差があるかどうかにこだわるのをやめ、p値のみを科学的根拠とするのは避けるべきだという趣旨の声明です。
有意差がないことが明らかとなった研究結果は、一見ネガティブにとらえられがちですが、これまで一般的とされてきた理論や仮説に対する反証となったり、将来この分野の研究の基礎となったりする可能性があるのです。
統計的な有意差がなかったときの対処法
統計的に有意差がない、つまりp値が0.05よりも大きくなってしまう原因はさまざまですが、よくあるのは「症例数が少なかった」というケースです。症例数が不足していたため有意差が認められない場合は、論文の考察において症例数不足によって検出力が十分ではなかったことを記載しましょう。
また、臨床試験の計画段階において算定したサンプルサイズが適切だったかどうかも検証しましょう。統計学上、最低30のサンプルがあれば経験的に信頼性が高い区間推定が可能とされていますが、サンプルサイズが大きいほど精度は高まります。必要に応じて追加試験を行ったり、先行研究の結果とあわせてメタ分析を行ったりすることも検討します。
期待していた有意差がみられなかったときに、十分な検証や課題の検討を行わず、論文の考察に「有意な傾向があった」と記載してはいけません。実際に分析して得られたp値を併記し、「有意差はみられなかった」と明記しましょう。
医学分野の論文において最も重要なのは、クリニカルクエスチョン(臨床的疑問)です。臨床上、直面する課題や疑問点などをクリニカルクエスチョンとして掲げ、仮説を立てます。そして、研究計画に基づいて実験や試験を行い、分析し、なぜそのような結果が出たのかをしっかりと考察することが大切なのです。つまり、「有意差はみられなかった」という結果はクリニカルクエスチョンに対する紛れもない事実であり、十分に考察を行うことで論文として成立させることが可能です。
有意差がない結果も科学的には重要である
例えば、「既存の治療法と比較すると、新たな治療法ではAという検査項目が改善した」ということを論文で明らかにしたいとします。実際に臨床試験を行い、既存の治療法と新たな治療法で有意差が認められた場合、「新たな治療法のほうが、Aという検査項目が改善する」という結論が見いだせます。
一方、新たな治療法に期待していたにもかかわらず、実際に臨床試験を行ってみた結果、有意差が認められないこともあります。その場合、結論としては「Aという検査項目については、既存の治療法と新たな治療法に差はない」ということになります。
後者は論文としてはあまり目立った功績ではないように思われがちですが、決して役に立たない研究だったということではありません。これから先、医師や患者が治療法を選択するうえで検討材料となったり、さらに新しい治療法へと発展する礎となったりする可能性があるからです。
そのためにも、臨床的に意味のある差が見いだせなかったのか、もしくは症例数が足りないことによる検出力不足だったのかを考察で明示することが大切です。「有意差がない研究は出版されにくい」というイメージをもってしまいがちですが、たとえ有意差がない結果が出たとしても、嘆く必要はありません。症例数が十分であり、きちんと検証されたデータであれば、有意差がない結果であっても科学的に重要であることに変わりないのです。
参考文献
ASA — The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose
Nature ダイジェスト — Vol.13 No.6 P値の誤用の蔓延に米国統計学会が警告