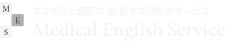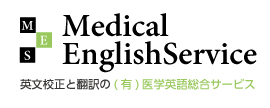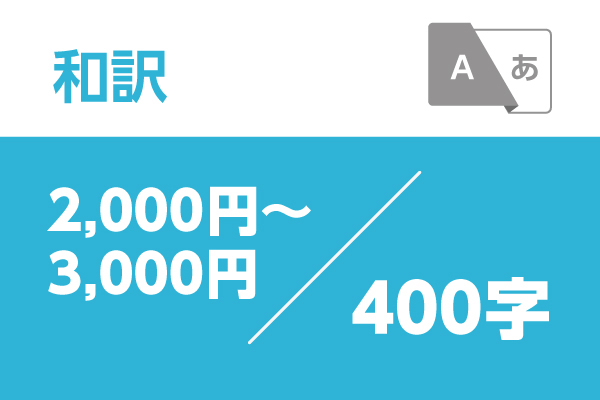英語の豆知識 (2):多義語
医学英語総合サービスでは、弊社の校正・翻訳・投稿支援を利用くださったお客様に、月1回お知らせレターを配信しております。One Point Englishのショートメッセージも配信していますのでご紹介します。
英語には一つの単語に複数の意味があるものが多く存在します(多義語)。
多義語のさまざまな意味は、歴史的(ルーツ)な繋がりの中で形成されたのだそうです。
たとえば、“mean”という単語を見てみましょう。
一見同じ綴りでも、実はまったく異なるルーツから来た意味が混在しています。
1.“What do you mean?” の mean は動詞で「意味する」という意味。この語はゲルマン語系で、元々は「intend to convey(頭の中にあるものを、運び伝える)」という意味を持っていたそうです。つまり、「相手に伝えようとしている内容は何か?」という問いかけなんですね。
2.一方、“a mean person” の mean は形容詞で「意地悪な」「ケチな」「下品な」という意味。これはラテン語の「common(一般的な)」に由来し、そこから「平均的な」「平凡な」、さらには「卑しい、下劣な」へと意味が派生したといわれています。
3.さらに、統計の分野でおなじみの “mean ± SD”(平均値 ± 標準偏差)の mean は、「中間」や「媒介」を意味するラテン語の「medium(メディア)」が語源。データの中心的な値という意味で使われています。
このように、「mean」という一語だけでも、異なる語源・意味が複数存在しており、それぞれの背景を知ることで理解が深まります。多義語の面白さは、単語の奥にある“歴史”や“文化”を知ることにあるのです。
次に、“head”という単語を見てみましょう。
「頭」という意味がまず思い浮かびますが、そこから派生して「リーダー(head of the company)」、「先端(head of the table)」、「見出し(headline)」など、実に多様な使い方が存在します。これらは一見バラバラに思えるかもしれませんが、すべて「最上部」や「先頭にあるもの」という共通イメージから広がっています。
こうした意味の広がりには、文化的背景や言語の進化が大きく関わっています。時代の流れとともに、人々の生活や考え方が変わることで、言葉の使い方も柔軟に変化してきたのです。
多義語を理解するカギは、「意味ごとに覚える」のではなく、「核となるイメージ(コア・ミーニング)」をつかむこと。ひとつの単語がどのように意味を広げてきたのか、そのルーツをたどることで、英語の理解がより深まり、記憶にも残りやすくなります。
- 2025.04.14 英語の豆知識 (2):多義語
- 2025.02.21 医学英語論文の書き方マニュアル – 33:「they」の単数使用 : 言語の柔軟性や社会の変化を反映
- 2025.01.10 医学英語論文の書き方マニュアル – 32:英語のスタイルは時代とともに変わります(例:Diagnose、Previous study )
- 2024.12.16 医学英語論文の書き方マニュアル – 31:[性同一性障害] gender identity disorderは時代遅れの言い方?
- 2024.11.12 医学英語論文の書き方マニュアル – 30:【基準】standard と criterion の違い